こんにちは。千葉県市川市にある歯医者「本八幡駅前ミツル歯科」です。
親知らずが生えている、もしくは埋まっている場所の歯ぐきが突然腫れて痛みを感じた経験がある方は多いのではないでしょうか。特に20代から30代にかけて、この症状が現れることが多く、日常生活に支障をきたすほどの痛みや違和感を伴う場合もあります。
親知らずの腫れは一時的なものと思い込んで放置すると、さらに悪化する可能性もあるため、正しい知識と対処法を知っておくことが大切です。
今回は、親知らずの周囲の歯ぐきが腫れる原因やその際に自分でできる対処法、治療法、そして予防法についてわかりやすく解説します。
親知らずの周囲の歯ぐきが腫れる原因
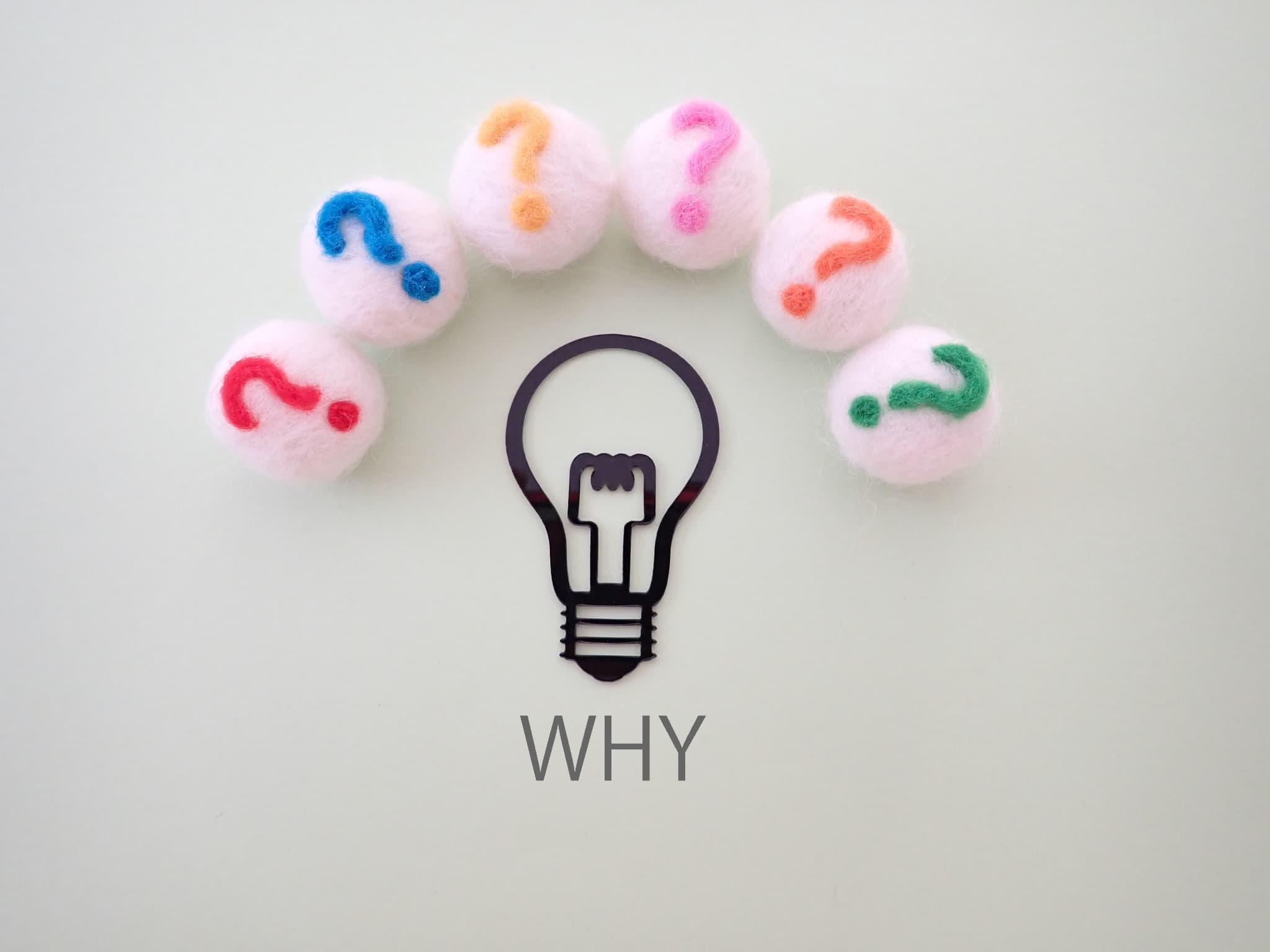
親知らずの周囲の歯ぐきが腫れる背景には、いくつかの要因があります。ここでは代表的な原因について具体的に解説します。
智歯周囲炎(ちししゅういえん)
親知らずの周囲の歯ぐきの腫れの最も一般的な原因が智歯周囲炎です。これは親知らずの周囲に細菌が侵入し、歯ぐきが炎症を起こす状態です。
特に親知らずが斜めに生えていたり、半分だけ露出していたりすると、歯と歯ぐきの間に食べかすや汚れが溜まりやすくなります。これにより細菌が繁殖し、炎症が引き起こされ、腫れや痛み、口が開きにくいなどの症状が現れることがあるのです。
親知らずの位置異常や生え方
親知らずは正常にまっすぐ生えることが少なく、斜めや横向き、あるいは完全に埋まったままになることがあります。このような位置異常により、歯ぐきが圧迫されたり、隣の歯に影響を与えたりして炎症を引き起こすことがあります。
また、生えかけの親知らずが一時的に腫れることもあり、この場合も放置すると炎症が悪化する恐れがあります。
免疫力の低下
体調不良やストレス、寝不足などで免疫力が落ちているときには、普段は炎症を起こさない程度の細菌でも歯ぐきが腫れることがあります。特に親知らずは歯磨きがしにくい場所にあるため、磨き残しが原因で炎症を起こすことがあるのです。
親知らずの周囲の歯ぐきが腫れたときに自分でできること

腫れが起きた場合にはすぐに歯科医院を受診するのが理想ですが、すぐに行けない場合には応急処置として自分でできることもあります。
口の中を清潔に保つ
歯ぐきの腫れがある場合でも、可能な範囲で口腔内を清潔な状態に保つことが重要です。特に親知らずの周囲を優しくブラッシングし、食べかすを残さないようにしましょう。
また、殺菌効果のあるうがい薬を使ってうがいをすることで、細菌の繁殖を抑えることができます。うがいは1日に数回、食後と就寝前に行うのが理想です。
冷やして炎症を抑える
腫れている部分を冷やすことで一時的に痛みや腫れを和らげることができます。
ただし、直接氷を当てるのではなく、冷たいタオルや保冷剤をタオルに包んで、頬の外側から当てるようにしてください。長時間の冷却は逆効果になることもあるため、10〜15分程度を目安に冷やすようにしましょう。
安静にして免疫力を回復させる
腫れが起こっているときは体が炎症と戦っている状態です。無理に動き回ったり夜更かしをしたりすると、免疫の働きが弱まり症状が長引く原因になります。できるだけ体を休め、バランスの良い食事と十分な睡眠を心がけましょう。
市販薬を服用する
市販の痛み止め(鎮痛剤)を使うことで一時的に痛みを和らげることができます。
ただし、薬はあくまで対症療法であり、根本的な解決にはならないため、あくまで歯科医院を受診するまでの一時的な措置と考えてください。
親知らずの周囲の歯ぐきが腫れたときの治療法

実際に歯科医院で行われる親知らず周囲の腫れに対する治療法について解説します。
抗生物質や消炎薬の処方
炎症が起きている場合、まずは抗生物質や消炎鎮痛薬を用いて炎症を抑える治療が行われます。腫れや痛みが強い状態では、すぐに抜歯できないことが多く、まずは薬で炎症を鎮めることが優先されます。
数日間の服薬によって症状が落ち着いた段階で、抜歯などの次の処置に移行します。
親知らずの抜歯
根本的な解決を目指す場合、多くのケースで親知らずの抜歯が勧められます。特に繰り返し炎症を起こす場合や、今後のトラブルが予想されるような位置の親知らずであれば、早期の抜歯が望ましいとされます。
抜歯は簡単なものから、口腔外科での手術が必要な複雑なケースまであり、レントゲンやCTなどの画像診断をもとに治療計画が立てられます。
定期的なメンテナンスと経過観察
抜歯をすぐに行わない場合でも、親知らずの状態を定期的にチェックすることが重要です。歯科医院では専門的なクリーニングやレントゲン撮影によって、親知らずの変化を確認し、問題が起こる前に対処できるようにします。
親知らずの周囲の歯ぐきが腫れるのを防ぐには

親知らずによる腫れを予防するためには、日々のセルフケアに加えて、歯科医院での定期的な管理が重要です。以下では、予防のために実際に行える具体的な方法をご紹介します。
親知らず周辺を意識した丁寧な歯磨き
親知らずは奥に位置しているため、歯ブラシが届きにくく、プラーク(歯垢)が溜まりやすい場所です。そのため、通常の歯磨きでは磨き残しが起こりやすく、腫れの原因となります。
対策としては、ヘッドが小さめで先端が細い歯ブラシを使い、歯ぐきとの境目を意識しながら磨くことが大切です。さらに、タフトブラシという部分磨き用のブラシを併用すると、親知らずの周囲にある細かい隙間にも届きやすく、磨き残しを防ぐことができます。
1日2〜3回、食後と就寝前に丁寧なブラッシングを習慣づけましょう。
デンタルフロスや歯間ブラシの活用
歯と歯の間に溜まった汚れや食べかすは、歯ブラシだけでは除去しきれません。親知らずの隣にある第二大臼歯との間に汚れが残ると、炎症やむし歯のリスクが高まります。そこで、デンタルフロスや歯間ブラシを使って歯間清掃を行うことが大切です。
マウスウォッシュで細菌の繁殖を抑える
日常的にマウスウォッシュ(洗口液)を使用することで、口腔内の細菌の繁殖を抑える効果が期待できます。特に、抗菌作用のある薬用タイプを選ぶと、歯ぐきの腫れや炎症を予防しやすくなります。
ただし、マウスウォッシュだけではプラークの除去はできないため、日々のブラッシングと組み合わせて使用することが大切です。
定期的な歯科検診とクリーニング
セルフケアだけでは取りきれない汚れや、目視できない問題を早期に発見するためには、定期的に歯科検診を受けることが欠かせません。
特に親知らずが斜めに生えていたり、半分埋まっていたりする場合は、経過観察が重要です。レントゲン撮影や口腔内診査により、炎症や膿の有無、隣接歯への影響などを確認することができます。
さらに、歯石の除去や専門的なクリーニング(PMTC)を受けることで、炎症を未然に防ぐことができます。
食生活と生活習慣の見直し
歯ぐきの健康を守るためには、口腔内のケアだけでなく、全身の健康状態を整えることも重要です。
ビタミンCやビタミンB群、亜鉛などは歯ぐきの炎症を抑え、治癒を促進する働きがあります。野菜・果物・魚介類・豆類などをバランスよく摂ることで、免疫力を高めることができます。
また、ストレスや寝不足は免疫力の低下を招き、歯ぐきが腫れやすい状態となるため、規則正しい生活習慣を心がけましょう。
症状が出る前に抜歯を検討する
現時点で症状がなくても、将来的にトラブルが起こる可能性が高いと判断される場合は、予防的な抜歯も選択肢の一つです。抜歯には術後の腫れや痛みが伴うこともありますが、早めに対応しておくことで将来的なリスクを回避できます。
まとめ

親知らずの周囲の歯ぐきが腫れる原因は、智歯周囲炎をはじめとする細菌感染や生え方の異常、体調の変化による免疫低下などさまざまです。腫れや痛みを感じた場合には、早めに適切な対応をすることで悪化を防ぐことができます。
自分でできる対処法を実践するだけでなく、歯科医院で治療を受けることも大切です。また、普段からの口腔ケアや定期検診を通じて、親知らずのトラブルを未然に防ぐことも重要です。
親知らずは抜くべきかどうか悩むことも多い歯ですが、早めに歯科医師に相談することが健康な口腔環境を維持することにつながります。
親知らずを抜くべきかお悩みの方は、千葉県市川市にある歯医者「本八幡駅前ミツル歯科」にお気軽にご相談ください。
当院では、虫歯や歯周病治療だけでなく、小児歯科や矯正歯科、ホワイトニング、マタニティ歯科などさまざまな診療に力を入れております。ホームページはこちら、WEB予約も受け付けておりますので、ぜひご活用ください。
